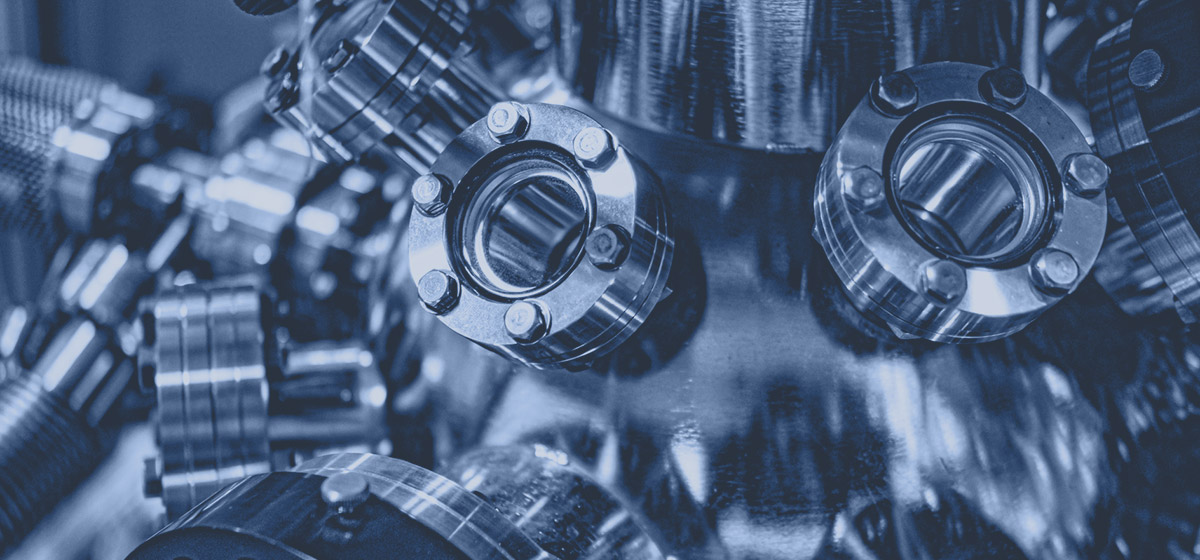「うちの装置に合うポンプって、結局どれなんだろう?」
「カタログを見ても、数字ばかりで違いがよく分からない…」
そんなお悩みはありませんか?真空ポンプの選定は、目標圧力やガス負荷、運用コストなど、考慮すべき点が多く複雑です。
この記事では要件に合わせた最適なポンプ方式から、性能を最大限に引き出すための周辺設計(前処理・据付)まで、真空機器の専門商社が、失敗しない選定プロセスを分かりやすくガイドします。

目次
真空ポンプ選びはここから!最初に決めるべき5つの必須要件
選定プロセスの9割は、この要件定義で決まります。
以下の5つのポイントを整理し、自社の「ものさし」を作りましょう。
- 目標圧力帯(どこまで真空にしたいか)
到達させたい真空度(到達圧力)と、実際に装置が稼働する圧力(運転圧力)はどのくらいですか? - 排気時間
容器を目標圧力まで排気するのに、どの程度の時間をかけられますか? - 排気する対象
排気したい容器の容積(L, m³)は?また、許容できるリーク量(空気の漏れ)はどの程度ですか? - ガス負荷
排気する気体の種類・量は?(水分、有機溶剤、腐食性ガス、粉塵の有無と、その温度は?) - 運用上の制約
24時間連続運転か、騒音レベルの規定、使用できる電源・冷却水、設置スペースの制限、TCO(総所有コスト)はどの程度を想定しますか?
▼【まずはここから!】要件整理シート
| 項目 | 自社の要求 | 備考 |
| ① 目標圧力帯 | Pa | 到達圧力と運転圧力 |
| ② 排気時間 | 秒 / 分 | |
| ③ 容器容積 | L / m³ | |
| ④ ガス負荷 | 水分、溶剤、腐食、粉塵の有無 | |
| ⑤ 運用制約 | 連続運転、騒音、電源、予算 |
関連記事:今さら聞けない「真空」とは?原理・種類・用途をわかりやすく解説!
カタログスペックに惑わされない!正しい性能の読み方
必要な条件が決まったら、次はカタログを正しく読み解く知識を身につけます。
定格値だけで選ぶと失敗のもとです。
- 最重要:排気速度曲線
カタログに記載の「最大排気速度」は、あくまで大気圧付近での値です。
実際に大切なのは自社が使いたい圧力帯(運転圧力)で、どれだけの排気能力があるか、という点です。「排気速度曲線」というグラフがそれを教えてくれます。 - 立上がり時間の概算方法
単純計算では「容器容積 ÷ 実効排気速度」で求められますが、これは目安です。
実際には配管の抵抗なども影響するため、安全マージンを持った選定が重要です。 - 押さえるべき5つの指標
- 到達圧力(Pa)
ポンプが単体で到達できる圧力の限界値。 - 排気速度S(m³/h, L/min)
一定時間に排気できる気体の体積。 - 許容大気圧
大気圧から運転を開始できるか否か。 - 許容ガス・パーティクル条件
流せる水分量や粉塵の限界。 - 騒音値(dB)
ポンプ稼働時の音の大きさ。
- 到達圧力(Pa)
ドライ?油回転?自社に合う真空ポンプの種類は
▼【簡易診断】自社に合うのはどのタイプ?
- Q1. クリーンな環境が最優先?(油分の混入は絶対に避けたい)
- YES → ドライ真空ポンプへ
- NO → Q2へ
- Q2. 水蒸気や粉体を多く排出する?
- YES → 水封式またはドライ式+前処理装置が有力
- NO → Q3へ
- Q3. 高真空・超高真空が必要で、その手前のポンプを探している?
- YES → 主ポンプを補助するドライ式または油回転式の前段ポンプを検討
- NO → 汎用の油回転真空ポンプも選択肢
関連記事:真空ポンプの種類を徹底解説!主ポンプから高真空ポンプまで仕組みと用途を紹介
最適な一台を見つける!圧力帯・ガス負荷で見るポンプ方式の選び方
ポンプ方式毎の得意な点、苦手な点を比較検討しましょう
研究・分析/前段向け(低〜中真空・小〜中流量)
前段とは、「主ポンプ(メインポンプ)」よりも前の段階に位置し、主ポンプの働きを助ける役割を持つポンプのことを指します。
この領域では、クリーンさとコンパクトさが求められることが多く、以下の方式が主流です。
| 方式 | メリット | デメリット・注意点 |
| スクロール | クリーン、低振動、静音 | 摩耗粉、チップシール交換 |
| ダイアフラム | 小型・安価、オイルフリー | 脈動、膜の定期交換 |
| 揺動ピストン | 比較的小型で高圧まで | 運転音、ピストンリング摩耗 |
いずれの方式も、多量の水蒸気や粉塵を直接吸引すると寿命を縮めるため、後述の前処理が必須です。
生産ライン/連続運転(中真空・中〜大流量)
耐久性と大排気量が求められる生産ラインでは、非接触式のドライポンプが活躍します。
| 方式 | メリット | デメリット・注意点 |
| クロー | 大排気量、耐久性高い | 運転音大きい、比較的高価 |
| スクリュー | 高圧縮比、効率良い | 起動時トルク大、精密なため異物に弱い |
| 多段ルーツ | 大排気量、シンプル構造 | 単体での圧縮能力が低い |
いずれのポンプも発熱や騒音が大きくなる傾向があり、据付時の防音・防振設計や適切な冷却が前提となります。
高真空の到達・維持
分析装置などの高真空領域では、ターボ分子ポンプ(TMP)が使われますが、これは単体では動作しません。必ず、その手前を排気する前段ポンプが必要です。前段ポンプには、クリーンなドライ式か、排気効率の良い油回転式が選ばれます。
関連記事:真空ポンプの仕組みをわかりやすく解説!用途や構造・選び方まで紹介
ポンプの性能と寿命を左右する“前処理”設計
最適なポンプを選んでも、前処理を怠るとすぐに性能が落ちたり、故障したりします。
ポンプを守るための重要な設計です。
- 蒸気対策
水蒸気や溶剤は、ポンプ内で結露すると性能低下や故障の原因になります。コールドトラップやクライオトラップで事前に冷却・捕集します。 - 粉塵対策
プロセスで発生する微粒子は、ポンプ内部を摩耗させます。吸気フィルタを設置し、粒子の大きさに合わせて適切なものを選びます。 - 腐食性ガス対策
ポンプの材質を耐食性の高いもの(SUS等)にする、不活性ガス(N₂)を流してガスを希釈する(N₂パージ)などの対策が必要です。 - 油拡散対策
油回転ポンプ使用時に、油の蒸気が真空チャンバー側へ逆流(バックストリーミング)するのを防ぐため、逆止弁やフォアライントラップを設置します。
真空ポンプの適切な設置環境とは?
カタログ通りの性能は、適切な設置環境があってこそ発揮されます。
- 据付
ポンプは必ず水平に設置し、アンカーボルトでしっかり固定します。振動が問題になる場合は、防振架台や除振台を検討します。メンテナンスのための作業スペース確保も忘れずに。 - 配管
排気抵抗を減らすためには「短く、太く、曲がりは少なく」が配管の三原則です。継手からのリークにも十分注意が必要です。 - 静音
ポンプ本体の機械音、配管からの放射音、床や架台からの振動音など、音の原因は様々です。まずは発生源を特定し、防音カバー、配管のラッキング、防振材など、優先順位をつけて対策します。
三弘エマテックでは、真空機器の総合商社として、真空ポンプの導入からアフターケアまで、一貫したサポートを提供しております。
真空ポンプ選定でよくある勘違い・つまずきポイント
最後に、多くの方が陥りがちな失敗例をまとめました。
- 定格排気速度(最大値)だけで選んでしまう。
→ 使う圧力帯での実効排気速度を見ないと、能力不足になる。 - ポンプ方式は合っているが、前処理や据付の設計が抜けている。
→ ポンプの寿命を著しく縮め、結果的にコスト増になる。 - 騒音問題をポンプ単体で解決しようとしてしまう。
→ 配管や架台など、周辺からの音も大きい。全体での対策が必要。
まとめ
今回の記事では、真空ポンプを選定する際の基本的な流れと、注意しておきたいポイントをご紹介しました。
ぜひ、御社の装置や運用条件に合ったポンプ選びの参考にしてみてください。
ただ、記事の内容はあくまで一般的な考え方です。実際の現場では、装置の構造やガスの種類、設置環境など、カタログだけでは見えない要素が選定の決め手になることもあります。
もし、少しでも「うちの場合はどうだろう?」と感じたら、ぜひ三弘エマテックにご相談ください。
これまで17,000台以上の真空ポンプをお客様にお届けしてきた実績をもとに、装置やプロセスの特性を踏まえた最適なご提案をいたします。