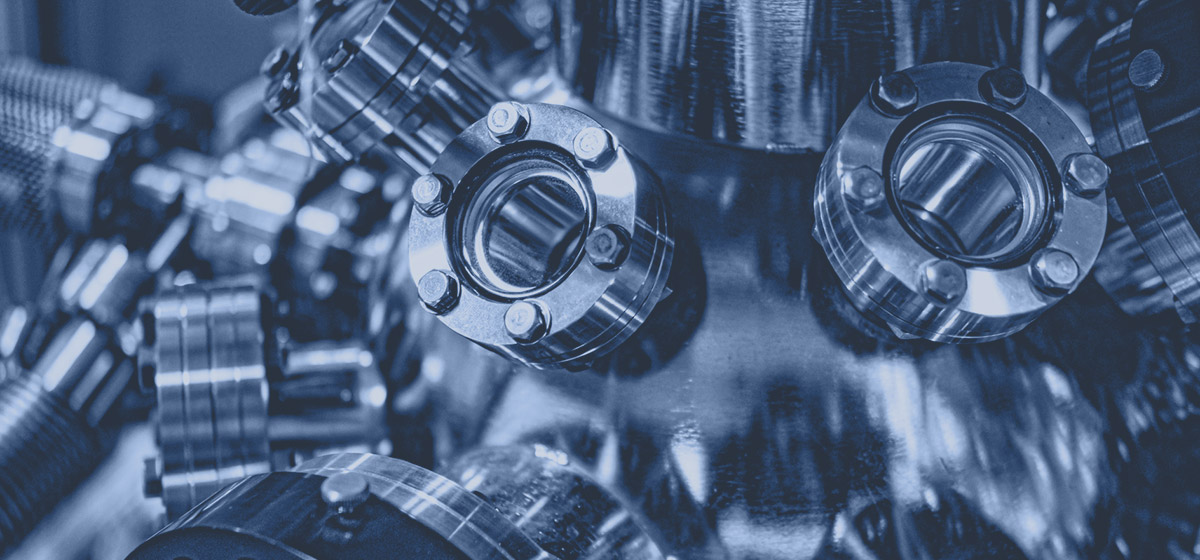本記事では、真空計の原理から用途別の種類を説明しています。
真空計を取り扱うものの原理がいまいち分かっていない、新しく導入を検討しているがどれが適しているかわからないなど、そういった疑問を解消します。 原理はわかったけれど、どのような真空計の導入が向いているか具体的に知りたい方もぜひ本記事を参考にしてみてください。
「真空計」と言っても、さまざまな種類の機器があります。
真空空間の何を測定するかによって、使用する真空計は異なるため、的確な機器を見極めなければなりません。
しかし、どの場面でどの種類の真空計を使用するといいのか、条件変更に見合う真空計の導入にはどの機器が的確か、が分からなくなってしまう場合もあるでしょう。 これらの困りごとが解決できるよう、真空計の種類と原理、三弘エマテック株式会社が取り扱っている機器をいくつか紹介します。
目次
真空計とは?
真空計とは、真空ポンプによって作られた気圧の下がった空間を周囲の空間と比較して、低くなった気圧を数値によって測定する圧力計のことです。
その測定方法はさまざまな手法があり、大まかに分けると「全圧真空計」と「分圧真空計」の2種類があります。
一般的に「全圧真空計」を真空計、「分圧真空計」を質量分析計と呼んだりもします
全圧真空計は、真空の空間内の分子や原子を対象として圧力を測定した方法で、分圧真空計は空間に存在する気体の組成を利用した方法です。
真空度合いは、低真空(10²~10⁵)、中真空(10⁻¹~10²)、高真空(10⁻⁵~10⁻¹)、超高真空(~10⁻⁵)の4つに分類され、真空計によって測定できる度合いも違っています。 2つの真空計について、それぞれ詳しく説明します。
全圧真空計とは
全圧真空計とは、測定する空間内の原子や分子の全てを対象としており、「圧力」が知りたい場合に使用する方法です。
その中でも、以下の3つの現象を計る方法で分けられます。
| 全圧真空計の分類 | 概要 |
| 機械的現象(絶対真空計) | 気体の機械的な動きである、物や面を押す力を利用した方法 絶対真空計とは、測定する気体の種類に関係なく圧力が測定できること |
| 気体の輸送現象 | 気体の熱の移動や対流する動きを利用した方法 |
| 気体中の電離現象 | 気体中の電離現象 |
3つの現象に分類される代表的な真空計と圧力範囲を紹介します。
機械的現象
機械的現象による、代表的な真空計5つとその測定可能な圧力範囲を紹介します。
油回転ポンプや圧力ボンベなどで変化している圧力を、ざっくりと確認するための真空計です。
| 真空計の名称 | 代表的な真空計 | 圧力範囲(Pa) |
| 液柱差真空計 | U字管真空計 | 約10²~10⁵ |
| 弾性真空計 | 隔膜真空計(ダイヤフラム真空計) | 約10⁻³~10⁵ |
| ブルドン管真空計 | 約10³~10⁵ | |
| 圧縮真空計 | マクラウド真空計 | 約10⁻²~10² |
| 圧力天秤 | 重錘型圧力計 | 約10~10⁵ |
気体の輸送現象
気体の輸送現象による、代表的な真空計6つとその測定可能な圧力範囲を紹介します。 真空計の中で「ピラニ真空計」が、一般的に使用されています。
| 真空計の名称 | 代表的な真空計 | 圧力範囲(Pa) |
| 粘性真空計 | スピニングロータ真空計 | 約10⁻⁵~10⁻² |
| クリスタルゲージ | 約10⁻²~10⁵ | |
| 熱伝導真空計 | ピラニ真空計 | 約10⁻¹~10⁵ |
| 熱電対真空計 | 約10⁻¹~10² | |
| サーミスタ真空計 | 約10⁻²~10² | |
| クヌーセン真空計 | クヌーセン真空計 | 約10~10⁵ |
気体中の電離現象
気体中の電離現象による、代表的な真空計3つとその測定可能な圧力範囲を紹介します。
高真空領域での圧力測定が、正確な真空計として重宝されています。
| 真空計の名称 | 代表的な真空計 | 圧力範囲(Pa) |
| 電離真空計 | 放射線真空計 | 約10⁻⁵~10⁻¹ |
| 冷陰極電離真空計 | 約10⁻⁴~1 | |
| 熱陰極電離真空計 | 約10⁻¹⁰~10⁻¹ |
分圧真空計とは
分圧真空計とは、測定する空間内の気体の種類とその組成を対象とし、「成分」が知りたい場合に使用する方法です。
分圧真空計は、電離真空計の原理に加えて磁場や電場などを利用して、イオンの質量分離が可能なことから「質量分析計」とも呼ばれます。
質量分析計の基本原理は、以下の3つから構成されます。
- 気体をイオン化する(イオン化部)
- イオンを質量電荷比(m/q)の違いで選別する(質量分離部)
- 選別したイオンを検出する(検出部)
3つの部分は、さまざまな方式の違いから異なる特性を生み出すため、知りたい情報に応じて使い分けることが必要です。
真空計の用途・できること
真空計は、真空空間の確認や数値化するだけでなく、真空の質を分析することもできます。
空間を真空にすると、空気が排除されるため水分を含む不純物が少なくなります。
この特徴を真空計で管理することで、以下のことに活用できるでしょう。
- 吸引
- 吸着
- ガスの収集
- 成形
- 液体の充填
- ガスの置換
- 酸化防止
- 凍結乾燥
- 乾燥
- 蒸留
- 濃縮
- 脱気
- 蒸着
- スパッタリング
- 断熱
- 冷却
利用先には、半導体製造装置のプラズマエッチング空間や冶金、有機合成の実験などの設備に設置されることもあります。 他には、イオンビーム装置や蒸着装置など、高い表面清浄度が求められる場面でも使用されます。
真空計の選び方
真空計を用いて、真空を測定する方法にはさまざまな種類があり、必要に応じて選択できます。
しかし、ひとつの手法だけでは、全範囲の真空を測定できないため、測定方法を合わせて使ったり、測定条件を合わせたりする必要があります。
特に、機械的現象を用いた圧力測定は気体の種類に依存しませんが、100Pa以下になると力が小さいため測定に限界があり、他の方法の利用検討が必要です。
複数の方法を組み合わせて、測定できる真空度範囲を広げた製品も販売されています。
以下の条件を確認し、真空計の種類を選ぶことができます。
- 検出圧力範囲
- 気体の種類
- 必要な精度と再現性
放射線などの周囲条件
真空計の種類
ここでは、弊社で取り扱う真空計を3つご紹介いたします。
それぞれの真空計の特徴を確認し、必要な条件を満たせるかどうか、ご検討ください。
| 製品名 | 真空計の種類 | 測定圧力範囲 |
| SWU10-U(アルバック社製) | ピラニ真空計 | 5X10⁻²~1X10⁵Pa |
| APG200シリーズ(エドワーズ社製) | ピラニ真空計 | 5X10⁻²~1X10⁵Pa |
| セラミックキャパシタンスマノメータ CCMT-Dシリーズ(アルバック社製) | 隔膜真空計(ダイヤフラム真空計) | 中、低真空 |
3つの製品を詳しく紹介します。
SWU10-U│アルバック社製
アルバック社製の「SWU10-U」はピラニ真空計で、主に真空ポンプや真空装置メンテナンス時の圧力確認に使用します。
2020年度日本真空工業会「イノベーション賞」を受賞した製品です。
USBケーブルを使い、スマートフォンへ接続し測定結果を手軽に確認でき、専用電源やディスプレイが必要ありません。
本体はAC電源も不要で、アルバック社製ピラニ真空計の中で最小・最軽量なため、持ち運びも簡単でどの場所でも測定が可能です。
APG200シリーズ│エドワーズ社製
エドワード社製の「APG200シリーズ」は、APG100シリーズから性能は落とさず、25%小型化を実現したピラニ真空計です。
製品上部のLEDライトリングの点灯方法の違いで、測定圧力を分かりやすく表示し、半導体分野でのメンテナンスや研究開発分野での実験管理を可能にします。
Mシリーズ、LCシリーズ、MPシリーズの3つがあります。
Mシリーズは、標準のタングステン/レニウムフィラメントが取り付けられ、大気圧~約5X10⁻²Paまでの圧力測定ができ、一般的な用途に使用できます。
LCシリーズは、耐食性の高いプラチナ/イリジウムフィラメントが取り付けられ、大気圧~1X10⁻¹Paまでの圧力測定ができ、腐食性のある用途でも使用できます。
MPシリーズは、プラチナ/イリジウムフィラメントが取り付けられ、大気圧~約5X10⁻²Paまでの圧力測定ができ、一般的な用途に使用できます。
セラミックキャパシタンスマノメータCCMT-Dシリーズ│アルバック社製
アルバック社製のセラミックキャパシタンスマノメータCCMT-Dシリーズは、セラミックの隔膜を利用した隔膜真空計です。
成膜装置のプロセス中や真空排気系の装置、各種製造装置などの圧力モニタとして、ガスの種類に関係なく精度よく測定可能です。
セラミックの隔膜を使用しているため耐腐食性に優れ、再現性の高さから正確な圧力測定ができます。 1000D、100D、10D、1Dの4つのシリーズがあり、これらは測定フルスケールの違いがあり、シリーズの数字が大きくなるほど、測定フルスケールも大きくなります。
真空計でお困りなら三弘エマテックへご相談ください
真空計の原理や用途、選び方、種類を紹介しました。
真空空間を作る時に必要な真空計は、さまざまな種類があります。
真空度の精度や空間の気体の種類など、測定条件を満たす真空計の選択が必要です。 真空計の選択や真空技術に関して、ご不明点やご質問があれば、お気軽に三弘エマテックまでご相談ください。